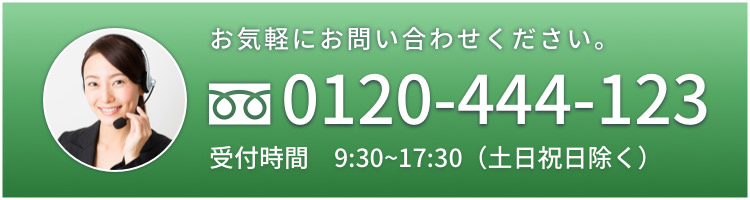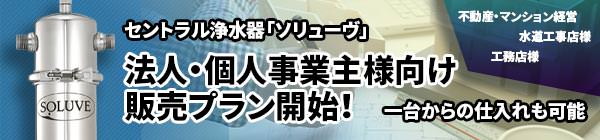全国初「みやぎ型」水道運営の全貌 ~民間委託の経緯と選挙での賛否両論
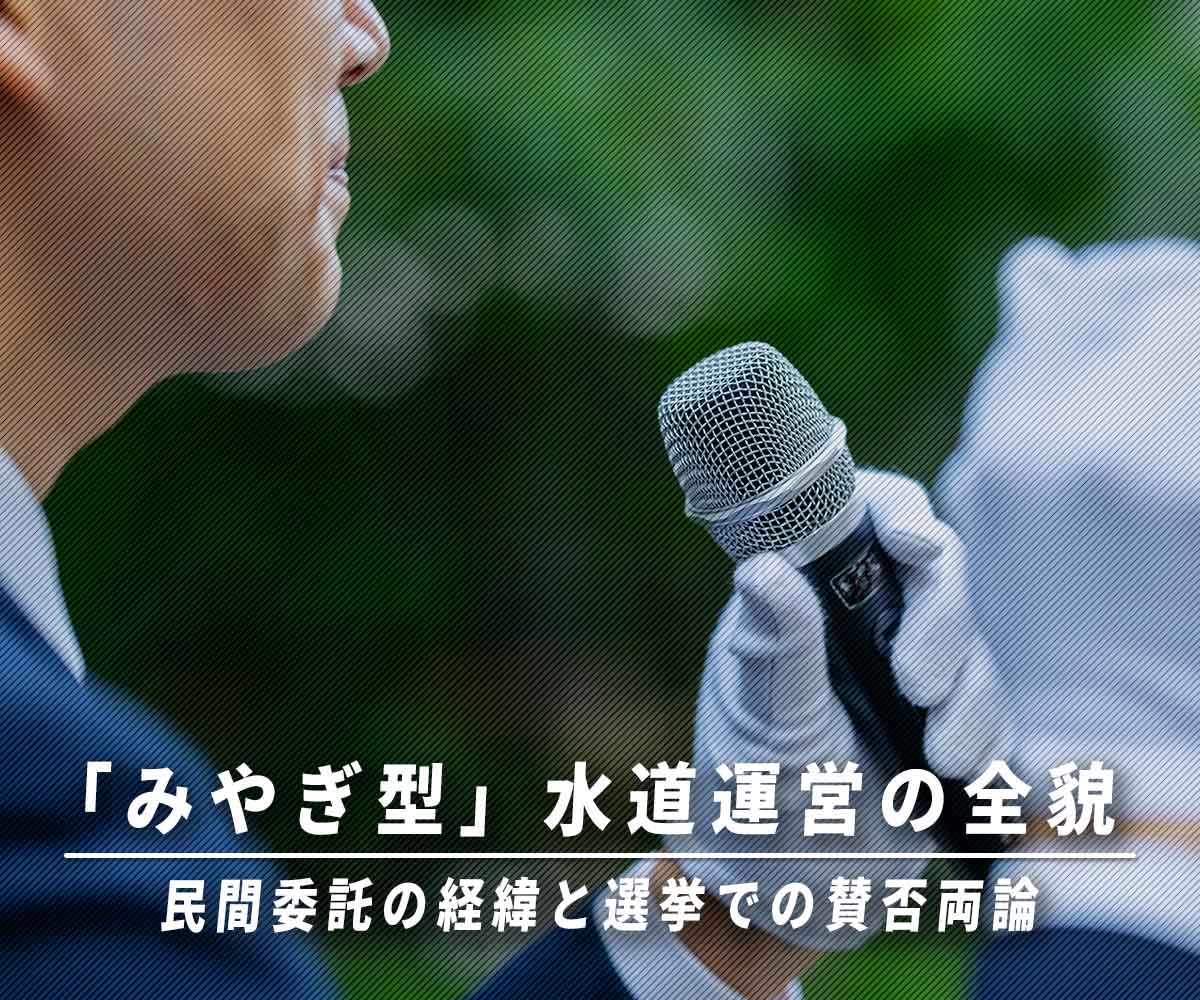

「今回の宮城県知事選で水道運営が争点の一つになりましたね。」
「確かに気になりますね。では、解説します。」



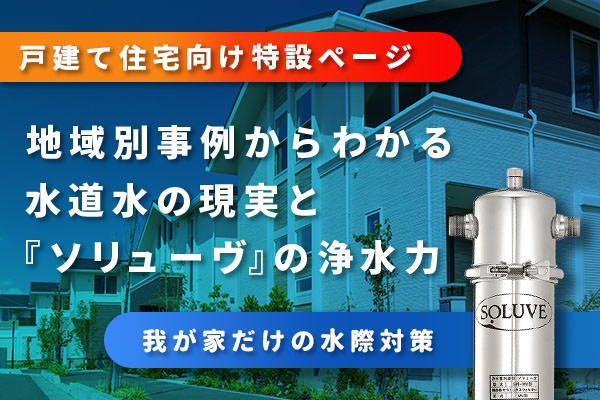

まずは自己紹介
弊社、株式会社メイプル・リンクは、創業34年のセントラル浄水器メーカーです。セントラル浄水器『ソリューヴ』の企画・製造・販売を行なっております。長年セントラル浄水器の販売を行なっている弊社が、気になる疑問についてお応えします。
宮城県知事選挙で再燃する水道事業の改革
宮城県知事選(26日投開票)で、県が2022年に始めた上下水道と工業用水の運営を民間に委ねる「みやぎ型管理運営方式」が、21年の前回知事選に続き争点の一つとなっている。 「民間の知恵と工夫で将来の料金高騰を抑える」と主張する現職に対し、新人は効果を疑問視し、「再公営化」を訴える候補も。事業の枠組みは複雑で、県の水道事業改革は検討当初から賛否両論があった。
河北新報 「宮城県知事選挙で再び争点「水道みやぎ」導入の経緯って?<かほQチェック>」より引用
3年前、宮城県は水道関連施設を所有したまま、その運営権を民間企業に一括売却した。このことが、知事選(26日投開票)の争点に急浮上している。民間の力を採り入れて急な値上げを防ぐのが県の狙いだが、「命に関わる水インフラは公営であるべきだ」との主張も広がる。なぜ、いま「水道」なのか。
県は、この仕組みを「みやぎ型管理運営方式」と名付け、2022年4月から全国初の取り組みとして始めた。「民営化」ではない「官民連携事業」と説明する。
朝日新聞 「「水道」論かけあう知事選 値が張る宮城、新方式で料金は下がった?」より引用
宮城県では、2025年10月26日の知事選挙を前に、水道事業の運営を民間に委ねる「みやぎ型管理運営方式」が大きな争点となっています。この方式は、2022年4月に全国で初めて導入されたもので、上下水道と工業用水の運営権を民間企業に20年間委託するものです。現職の主張では、民間の知恵を借りることで将来の料金高騰を抑えられる一方、新人候補からは効果の疑問視や再公営化の訴えが相次いでいます。
水道は、日常生活に欠かせないインフラです。料金の高さが続く東北地方で、この改革は県民の生活に直結するテーマです。

「県民にとっては、とても身近なことなので関心の高いテーマですよね。」
改革の始まり ~2017年の議論から水道法改正へ
「みやぎ型管理運営方式」のルーツは、2017年に遡ります。この年、県議会で水道事業の運営権売却に関する調査費が初めて計上されました。それ以前の2016年末には、国に対して水道法の改正を要望する動きがありました。旧来の水道法では、事業を完全に公営で運営するか、完全に民営化するかの二択しかなく、柔軟な官民連携が難しかったのです。
県の狙いは、人口減少が進む中で水道料金の上昇を抑えることでした。そこで、運営権のみを民間に委託し、認可や所有権は県が保持する形を求めました。この働きかけが実を結び、2018年12月に改正水道法が成立。県が認可を保持したまま、運営権を民間に移すコンセッション方式が可能になりました。
県議会での審議と条例改正
改正法成立後、県は上下水道と工業用水の運営を、特定目的会社に20年間委託する計画を具体化しました。民間の知見を活用し、事業の効率化を図るのが目的です。2019年11月の県議会定例会では、この導入を可能にする条例改正案が審議されました。採決の結果、賛成多数で可決されましたが、反対意見も根強く、賛成39、反対19という票決となりました。
最大会派を含むいくつかの会派が賛成した一方、共産党や社民党、無所属の議員らが反対を表明。立憲民主党系の会派内でも意見が分かれました。批判の声として、「安全性を犠牲にコスト削減を優先しているのではないか」「民間に頼らざるを得ない仕組み自体に問題がある」といった指摘が挙がりました。
県側は、これを「完全民営化ではなく、県が給水責任を負う官民連携」と強調。浄水場などの運転管理は従来から民間に委託されていたため、根本的な変化ではないと説明しました。

「なるほど。」
みやぎ型の仕組み ~業務の変化と三つのアシスト
「みやぎ型」の核心は、運営の効率化です。県が所有権と最終責任を保持しつつ、民間企業が出資する特定目的会社に運営権を委託します。2021年3月には、国内の水処理大手や海外企業のグループを優先交渉者として選定。同年12月に正式契約を締結しました。
主な業務の変化
導入前後の業務分担は以下の通りです。浄水場などの運転管理は変わらず民間委託ですが、水質改善のための薬品や資材の調達、設備の修繕・更新工事は民間に移行しました。一方、県は料金設定の権限を持ち、水質検査や管路更新を継続して担います。
- 運転管理:民間委託(変更なし)
- 薬品・資材調達:民間移行
- 設備修繕・更新:民間移行
- 料金設定:県保持
- 水質検査・管路更新:県継続
運営会社はメタウォーターが議決権株式の51%を保有する特定目的会社で、維持管理会社とは業務委託契約を結びます。維持管理会社には海外企業が筆頭株主ですが、運営会社が不履行時に契約解除できる仕組みを設けています。
県が用意した三つのアシスト
民間事業者がノウハウを最大限発揮できるよう、県は三つの支援を講じました。まず、スケールメリットとして、上下水道など9事業を一社にまとめて委託。一括管理や薬品の大量購入でコストを削減します。次に、自由度を高め、水質基準のみを定め、管理手法を民間に委ねます。最後に、契約期間を4~5年から20年に延長し、設備投資やシステム開発の時間を確保しました。
これにより、運営会社は運転状況や水質を一元監視するシステムを開発。情報を県や市町村と共有するプラットフォームも構築しました。人件費削減や設備更新の最適化が進み、今年からは関連施設に太陽光パネルを設置して電力負担を軽減しています。
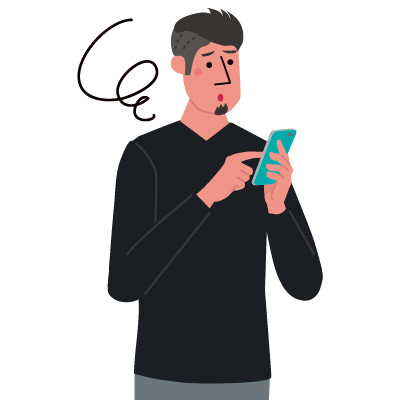
「海外企業が維持管理会社の筆頭株主なんですか…。」
住民説明会と前回選挙での反応
事業の難解さが課題の一つでした。2021年4月から6月にかけて、県主催の住民説明会を4会場で計6回開催しましたが、参加者は総定員の半分にも満たない198人にとどまりました。複雑な枠組みが、関心の低調を招いたようです。
2021年知事選挙での争点化
県議会での可決から3カ月後、2021年10月の前回知事選挙でこのテーマが浮上しました。現職と新人の一騎打ちとなり、現職は「人口減少による料金上昇を抑えられる」と必要性を訴えました。一方、新人は「手続きを凍結し、県民投票で意向を確認すべき」と主張。結果、現職が大差で勝利し、投票率も前回より上昇しました。
この選挙を機に、事業は2022年4月にスタート。紆余曲折を経ての導入でした。
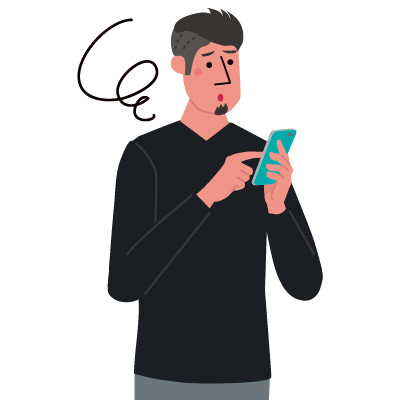
「当時は、分かりにくい内容だったこともあって関心がそこまで集まらなかったんでしょうか。」
3年目の成果 ~コスト削減と料金への影響
導入から3年が経過し、事業は順調に推移しています。運営会社は20年間で従来比337億円のコスト削減を目指しており、業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めています。浄水施設の薬品一括購入や中央監視システムの導入により、保守点検の拠点を集約。スタート時の約270人の社員数は約240人に減りました。
具体的なコスト削減効果
開始から2年間で、想定より4億円上回る削減を実現。2024年度の運営会社決算は純利益6億6,400万円で計画を15.1%上回り、維持管理会社も純利益2,900万円を確保しました。深刻なトラブルもなく、滑り出しは良好です。ただし、物価高や電力料金の上昇で経営環境は厳しくなっています。
料金面では、2024年度から5年間、大崎広域水道事業への供給単価を1立方メートル当たり1.6円引き下げ、仙南・仙塩広域水道事業を7.0円引き下げました。最終消費者の水道料金は市町村が設定するため、直接的な影響は少ないですが、全国的な値上げ圧力の中で一定の歯止めとなっています。
旧方式との比較
旧方式では20年間の総事業費が3,314億円と試算されていましたが、新方式で約1割の337億円を削減できる見込みです。この効果は、25年後に控える大規模設備改修の負担軽減に寄与します。

「なるほど。」
東北の高水道料金と地理的格差
宮城県の水道料金は全国的に見て高止まりしています。日本水道協会のデータでは、2024年度の家庭用水道平均料金(10トンあたり)が2,172円で、全国3位。北海道や青森に次ぐ水準です。過去10年も3~4位を推移しています。
料金格差の要因
東北地方全体で料金が高い理由は、面積の広さによる配管管理費の増大、人口の少なさによる売上量の低さ、冬の凍結対策費の負担です。宮城県内でも、2020年度の1カ月20立方メートル当たりの料金(家事用、下水除く)は、全国平均約3,300円に対し、仙台市が3,553円、栗原市が5,481円、丸森町が5,010円とばらつきが大きいです。
県の説明では、西部山間部のダムから取水し、各自治体に供給するため管路が長く、地域ごとの整備コストが上乗せされるのが原因です。こうした地理的条件が、改革の必要性を高めています。
- 都市部(例: 仙台市):使用量が多く料金が低め
- 中山間地・過疎地:料金が高くなりやすい
- 北日本:凍結防止費用が増大
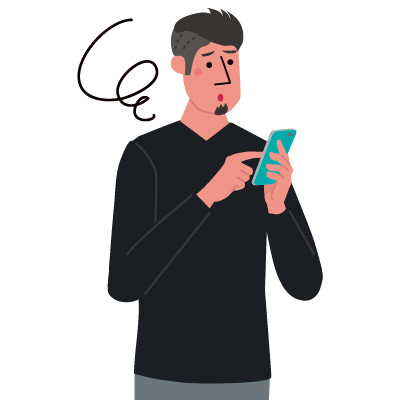
「供給エリアが広くなれば、管理コストも上がりますし、一方で需要が少ないとなると水道料金が高くなるのは想定できますね。」
選挙での賛否両論 ~現職と新人の主張
今回の知事選挙では、「みやぎ型」が再び争点に。夏の参院選での批判がきっかけとなり、外資参入への懸念が広がりました。
現職の主張
現職は、水道法改正を自ら推進した点を強調します。旧法の二択を脱し、所有権と責任を県が保持しつつ、毎日水質チェックを可能にしたと説明。コンセッション方式により、9事業所をデジタル技術で1カ所に集約。薬品調達の効率化や機械導入で経費を抑え、20年で3,300億円以上の負担を337億円削減できたと主張します。
外資系企業については、日本で80カ所以上の浄水場を管理し、社員1万人のうち外国人は50人だけと、実績を挙げて安心を呼びかけます。
新人候補の主張
一方、無所属の元参院議員の新人は、公営を前提とし、民営化のコストカット効果を疑問視。未来予測に基づくため不確実で、料金が全国3位の高止まりのままですと指摘します。外資が管理会社の51%を占める点に懸念を抱き、経済摩擦時のリスクを挙げ、「水が出ない事態」を危惧。再公営化で料金を下げたいと訴えます。
別の無所属の元県議の新人は、水道法改正の歴史を振り返り、PFI法の影響を指摘。管路更新と併せて料金低減を目指したものの、解約に2億円かかるとし、財務諸表をチェックして安全性や効果がなければ解消を検討すると述べます。「社会の実験場になるべきではない」と、検証の必要性を強調します。
こうした賛否は、命の水を公営で守るか、民知で効率化するかという価値観の違いを反映しています。外資は「黒船」のように見なされがちですが、日本で160施設以上の運転管理を担い、雇用者の9割超が日本人という実績があります。契約解除の取り決めもあり、県が最終責任を負う構造です。

「外資系企業の資本比率の問題であって、日本人の雇用の問題ではないですからね。契約解除の取り決めというのも気になりますね。海外でも一度は民営化したものの再公営化が議論された例もありましたよね。」
今後の展望と県民の視点
「みやぎ型」は、コスト削減の成果を上げつつ、住民の実感が薄い面もあります。供給単価の引き下げは卸売レベルで、末端料金への波及が限定的だからです。一方で、値上げ抑制の役割は果たしており、長期的に見て県民負担の軽減につながる可能性があります。
選挙を通じて、この方式の是非が問われます。公営回帰の声が高まる中、県は水質基準を法令より厳しく設定し、毎月の抜き打ち検査を実施。品質維持に努めています。

「なるほど。」


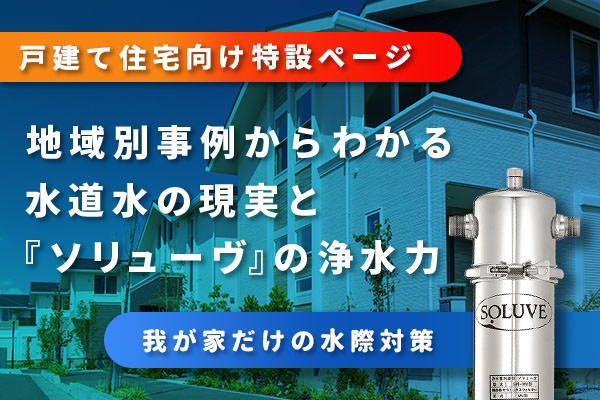

「いかがでしたでしょうか。全国初「みやぎ型」水道運営の全貌と民間委託の経緯を含めた選挙での賛否両論について解説しました。」


「はい。よく分かりました。」
おすすめ関連記事
「以下の関連記事も、是非ご覧ください。」